書籍詳細
没落令嬢は狂おしいまでの独占欲で囲われる
あらすじ
不本意な政略結婚から逃れ、最愛の彼にお嫁入り!?
「君を俺の妻にする」
没落士族の令嬢・うたは、夜道で男に襲われそうになったところを警察官の馨に助けられる。うたの貧しい身の上を知り、過保護な愛情で包み込んでくれる馨。ところが、うたの不本意な政略結婚が決まり…。「君は俺のものだ」――独占欲を剥き出しにした馨に、彼のお屋敷で囲われることに!熱く求められ、熱情を刻まれる蜜月の日々が始まって…!?
キャラクター紹介
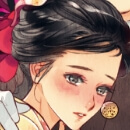
皆川うた(みなかわうた)
汁粉屋を営む、没落士族の娘。母を失い、父と二人暮らし。おっとりしているが、器用で芯が強い。

桐野 馨(きりのかおる)
元長州藩の維新志士の邏卒。役職は警部補。無口だが正義感が強く、うたには優しさを見せる。
試し読み
「ご主人様、奥様のお支度ができただよ」
「と、トミさん。奥様だなんて」
トミさんと一緒に玄関に向かうと、冬物の羽織袴姿の馨様が下駄を履き、土間で待っていた。
邏卒の制服も素敵だけど、着物もよく似合う。
廊下からだと、土間にいる馨様をかろうじて見下ろす形になる。
いつも見上げてばかりだけど、上から見る彼も素敵。
ぼんやり見惚れている私に、馨様が手を差し出した。
「ほれ、いってらっしゃい」
トミさんに軽く背中を押され、我に返る。
「い、いってきます」
私も下駄を履き、彼の隣に立った。
「見違えた。髪型ひとつで変わるものだな」
馨様が私の横顔をじろじろと見るから、照れてしまう。
「行こう。俺のかわいい奥さん」
大きな手が、私の手を引く。
外国では、夫婦が手を繫いで歩くこともあるらしいけど、この国ではまだそんな風景を見たことがない。
非常に照れくさかったけど、かわいいと言われた私の心は躍っていた。
馨様と一緒に馬車に乗り、賑やかな街に出た。
「ここが銀座……」
私はその街並みを見て呆然とした。
馨様のお屋敷周辺の街も、私にとっては華やかだったけど、ここはより一層すごい。まるで異国のよう。異国に行ったことはないけれど。
生まれも育ちも維新後に住んでいたのも、街から離れた寂れた土地だった私は、見るものすべてに目を奪われた。
煉瓦造りの二階建ての建物が大通りの両側にずらりと並んでいる。
二頭の馬で引く乗合馬車が、我が物顔で往来する。
その合間を縫うように、小型の馬車や人力車、大きな荷物を載せた荷車が通っていった。
行き交う人々はまだまだ着物の人が多いが、たまに洋服の婦人や、西洋風の帽子をかぶった紳士などを見かける。
通りの両端には等間隔で植えられた街路樹と、その間に街灯が立っていた。
「こんなに綺麗な街並みは見たことがありません」
白い煉瓦造りの建物の二階は外に出られるようになっており、柵を持った紳士が地上を見下ろしていた。
「あれはバルコニーと言う」
「ばるこにい」
「今後はこの地面に鉄の軌道を敷き、日本人が今まで見たこともない大型馬車を走らせる計画があるらしい」
「まあ。あの四、五人乗っている馬車よりも大きな馬車なのですか?」
「ああ、一両に二十五名ほど乗れるそうだ。運用開始は数年後とのことだ」
どんなものか想像もつかない私は、嘆息した。
今まで、移動といえばほとんど徒歩だった。
人力車はおまさちゃんのお稽古の帰りに送ってもらうときにしか乗ったことがない。
欧州式の馬車に乗ったのも、馨様と出会ってから数度だ。
「馨様はすごいですね。鉄道にも軍艦にも乗ったことがおありなんでしょう?」
「すごいのはそれを作った人たちだ。俺じゃない」
それはそうだけど。自分自身が世間知らずなので、自分が知らないことをたくさん知っている馨様のことを、素直にすごいと思ってしまう。
「さて、街並みを眺めているだけじゃなく、歩くとしよう」
「はいっ」
「まず洋服店へ行く」
「はいっ」
ガラスが嵌められた窓が珍しく、映る自分たちの姿をのぞきながら街を歩く。
こんなに心が浮き立つのはいつぶりだろう。
いつも自分を励まし、なんとかその日その日を送っていたことが噓みたいだ。
彼の大きな手が導いてくれる。それだけで心から安心することができた。
少し歩くと、ガラス窓の中に見たこともない色の布が現れる。
馨様は躊躇せず、その店の中に入っていった。
「いらっしゃいませ」
私はあんぐりと口を開け、その内装に見入った。
透明の宝玉を繫げたような、見たこともない照明器具が天井からぶら下がっている。
絨毯が敷き詰められた床は、下駄で踏むには不似合いな気がした。
そして、中央には商談をすると思われる大きなテーブルと椅子。
壁際には、洋装の女性のホトガラがたくさん飾られている。
その洋服も外で見た紳士が着ているようなものではなく、腰の後ろからお尻にかけて風船のように膨らんでいて、丈はつま先まで隠れるくらい長い。
政府高官や役人、邏卒などは洋服を着ることが主流となっている。
人力車の車夫にもズボンを穿いている人がいた。
しかしまだまだ女性の洋服は少ない。
高屋敷家の奥様も何回か洋服を着ているのを見かけたことがあるけど、そう頻繁ではない。普段は圧倒的に着物が多かった。
政府のお役人と違い、女性は仕事で洋服を身につける必要がないからだ。
「うた、好きな生地を選ぶんだ」
「はいっ?」
「二着は作りたいと思っている。少し前に、洋服を正装とするという法律ができたことを知っているだろ」
私は遠慮がちにうなずいた。
旅籠のお客様がそんなようなことを言っているのを聞いた覚えがある。
でも、正装なんてそれこそ、公的な仕事をしている人しか必要ないのでは。
馨様だって、制服以外で洋服を着ているのを見たことがない。
自分のものは持っていらっしゃるのかしら?
お店の雰囲気に圧倒されてびくびくしている私に、馨様は真面目な顔で言う。
「そのうち、公の場に妻を同行する場合は、洋装でなくてはならなくなる」
「ええっ。そうなんですか」
女性の洋装は男性に比べてなかなか浸透しない。
政府的には、裾から下帯が見えたり腿が見えたりする着物より、洋服を正装として普及させたいらしい。
野蛮な未開の地と見られるのがそんなに嫌なのかな。日本の人にとって、着物を自由に着こなすのは普通のことなのに。
「というわけで、このホトガラを見本にして選ぶもよし、店主と話しあうもよし。好きなように作るといい」
「ひいい」
私は慄いてしまう。
着物でも古着しか着たことがない私は、新品をあつらえたことがないのだ。
しかもそれが洋服となると、高価なのはわかるが果たして具体的にいくらかかるのか見当もつかない。
「だ、だめです。そんなに大金を使わせるわけには」
「そういう問題じゃない。妻に正しい身なりをさせることは、夫の義務だ。おかみさん、妻はこの通り遠慮深くてなかなか決まりそうにない。似合いそうなものを選んでくれ」
呼ばれたおかみさんはビシッと洋装を着こなし、名前もわからぬような、新しい髪型をしている。
「じゃあ桐野様、わしらは珈琲でも飲んで待ちましょう」
ご主人と馨様は優雅にテーブルにつく。そこへ洋風の前垂れをつけた若い女性が黒い泥水のような液体を運んできた。
なんだかいい香りがするけど、あれって珈琲ってやつかしら。
別のことに気を取られた私の手を、おかみさんが強く引く。
「まあかわいい奥様だこと。お任せください。洋服についてはこのサチ、ぷろふぇっしょなるですのよ」
「ぷ、ぷろふぇ……?」
どういう意味なのかしら。聞き取れもしなかった。何語かもわからない。
「とにかくこちらへおいでください」
おたおたしていた私は、サチさんに連れられて奥の部屋で体中を採寸された。
実際のものは私の体に合わせて作るけども、だいたいどんな形にするかを見本を着させてもらって選ぶことになった。
サチさんが絶対に私に似合うと言って差し出したのは、空色の生地に細かい花模様が織り込まれたドレスだった。
生地が折り重なり、お尻の部分が膨らんでいる。左右には切れ込みが入っていて、そこから別の布が見えていた。細かいひだがついている白っぽい布だ。
重ね着は着物の基本。洋服もこうして布を重ねるのがお洒落なのだと思うと、少し親しみが湧いた。
胸の前にはボタンとリボン。首の周りから肩にかけて白いレースが覆う。さらに袖口にもボタンやレースが。
私はおかみさんの手を借り、その見本を着た。
「あら、意外に動きやすい」
帯がないので、ボタンにさえ慣れれば体を通すだけでいい。
胸元がはだける心配もなし、裾が割れて足が見えることもない。
「そうでしょう。さあ、これでご主人の前に出てみましょう」
「えっ」
おかみさんは私の手を強く引いて、部屋のドアを開ける。
まだ自分で鏡をじっくり見てもいないのに、私は馨様の目の前に出されてしまった。
「いかがですか、桐野様。若々しい奥様なので、明るい色がいいと思いまして」
座っていた馨様が顔を上げ、目を見張った。
そのあとの言葉を待つけど、彼は黙ったまま。
「あの……似合いませんか」
やっぱり、私のような未熟な女に洋服は早かったかしら。
私が問うと、彼は我に返ったように瞬きをした。
「いや。似合ってる」
いそいそと立ち上がった彼は、近くに来て周りを回りながら全方位から私を見つめる。
「想像以上で驚いた」
「そ、そうですか?」
洋服を着たのが初めてなので、似合っているのかどうかもわからない。
「綺麗だよ。おかみさん、もう一着明るい色のものを見せてください」
「ありがとうございます。同じ形にしますか? もう少し腰回りがすとんとしていて、裾が広がっているものもありますが」
「興味あるな。ぜひ試着させてください」
というやりとりの結果、私は何着も見本を着て馨様の前に出た。
なにを着ても「似合っている」「綺麗だ」「かわいい」とべた褒めするので、こちらの方が恥ずかしくていたたまれない。
馨様って、そもそもこんな性格だったかしら。
初めて会ったときはほぼ単語しか話さない、不愛想な人だったのに。
最後の最後で「全部もらおう」と言う馨様を止めるので必死だった。
結局、そうそう着る機会がないという理由で押しきり、厳選して二着に抑えた。
「この生地やデザインでは春や夏にはちと暑うございますからね。そのときにまた作られたらよろしいですよ」
おかみさんの言葉に深くうなずき、馨様は洋服が出来上がったら手紙をくれるように頼んでいた。
一緒に靴や帽子、洋傘を注文し、お店を出たときにはぐったりと疲労困憊していた。
洋服を作ってくれたのはうれしい。
だけど、何着も着たり脱いだりするのはさすがに疲れてしまった。
「わあ、寒い」
店の中が暑かったので、冬の外気が頰に当たると気持ちいいくらいだ。
しかしそれも一瞬で、すぐに寒くなってきた。羽織を着ていても寒い。
「ほら、だからこれを肩に巻けと言っただろう」
馨様は持っていたショールを私の肩にかけた。
この前、汁粉屋に来たモダンな娘さんが身につけていたようなものだ。絹でできているものもあるそうだけど、冬は毛織物が人気だという。
店を出る直前にすすめられ、馨様が迷わず購入してしまった。
「あったかい……。馨様、本当にありがとうございます。なにからなにまで」
お店で今日注文したものの総額を聞いたら、倒れそうになった。
私とお父様が一年くらい余裕で生活できるくらいの金額だった。
よくよく考えてみれば、私は彼の正式な奥方ではない。
もしかしたらいつまでも内縁の妻だということもあり得る。
公の場など出る機会が訪れるかもわからないのに、なんだか申し訳ない。
「気にするな。夫として当然のことだ」
大きな身の丈のわりに小さな顔が、にこりと微笑む。
眩しすぎて、目を閉じてしまいそうになった。
彼は暗に、夫婦は心でなるものだと言ってくれているのだろう。
美しい微笑みは、お父様のせいで正式な夫婦になれない罪悪感を消し去ってくれた。
「しかし腹が減ったな。昼餉はなにがいい?」
さっきのお店で何着も着替えたりなんだりで、緊張するやら頭を使うやらで、お腹が減った。
「なにがいいんでしょう……」
極限までお腹が空いているので、逆になにも考えられない。
「そうだ。洋食はどうだろう」
「洋食っ?」
私はうつむいていた顔を上げた。
おまさちゃんの家で洋菓子をいただいたことはあるけど、洋食は食べたことがない。
「目が輝いたな。この通りに洋食の店があるはずだが」
洋食って、どんなのだろう。
パンやアイスクリーム、焼き菓子の他には、牛乳で煮た野菜やお肉があると聞いたことがある。
興味津々だけども、果たしてこの貧乏舌に合うだろうか。食べられなかったら申し訳ない。
うーん、でも、初体験はなんだって冒険よね。やってみないと、できるかどうかわからないもの。挑戦あるのみ……かな?
「あ、でも、馨様は洋食がお嫌いなのでは?」
私が袖を引っ張ると、彼は硬い表情でこちらを見下ろした。
洋食も食べたけど、やっぱり昔ながらの料理が好き、というようなことが手紙に書いてあった覚えがある。
「そんなことはない」
「でも、手紙に書いてありました」
「嫌いなんて書いてない。洋食より君が作った煮物の方がおいしいと書いたんだ」
そうだっけ。どうも、洋食に苦手意識があるような雰囲気を感じる。
だって、やけに必死だもの。
「麦や牛乳にはとても滋養があるそうだ」
「だから異国の人は体が大きいのですね」
「そういうことだろう」
並んで歩いていると、すぐに異様なにおいを放つ建物の前に着いた。
なんか……真夏にうっかり何日も置いたお豆の煮物みたいなにおいがするんだけど、気のせいかしら……。
横を見てみると、馨様は遠慮なく高い鼻を指でつまんでいた。
ガラス窓から中を見てみる。
西洋風の丸いテーブルの上に置かれた料理に、私は仰天した。
肉かなにかを焼いたような茶色の塊に、どろりとした黄色いものがかかっている。
塊は私の顔くらいあり、料理人がそれを客の目の前で切り分ける。
黒っぽい塊の中はまだ赤く、火がじゅうぶん通っていないのではないかと思われた。
「あれ……なんなんでしょう。黄色いものは牛乳?」
肉とは別の皿に、おそらくパンであろうものと、見たこともない野菜が載っていた。お芋の仲間かしら?
「さあ……西洋では牛の乳を固めたものを食べるというが、あれは半分溶けたそれだろうか?」
「牛の乳を固めて、またそれをどろどろにする意味がわかりませんね」
首を傾げる私の横で、馨様も不安げに窓の中をのぞく。
出張中に洋食を食べたことがある馨様も、よくわからない種類の料理みたい。
よく見るとあの料理人、日本の人っぽい。
もしや洋食の基本をよく知らないまま、自分流に洋風の材料を調理しているのでは?
「ごめんなさい馨様、私あれを食べきる自信がありません」
お肉を口に入れたお客さんが、首をひねっている。
誰も彼も、なにが正解なのかわからずに食べているのだろう。
「そうか。そうだな、食べ残しは料理人に失礼だものな。評判のいい店を調べてから来るとするか」
彼はどことなくホッとしたようにうなずいた。私が食べたがれば食べさせてくれただろうけど、彼自身はやっぱり洋食が苦手なのだ。
「では牛鍋はどうだ?」
「はい、そっちがいいです!」
牛鍋は薄切り牛肉を醤油と砂糖で味付けたお鍋だと聞いたことがある。それなら食べられそう。
「よし、決まりだ」
私たちは反対側の通りに渡り、牛鍋屋に向かった。
牛鍋は大当たりで、初めてだったけどとてもおいしく食べられた。
牛肉独特のにおいを、馴染みある醤油の香りが和らげていて、一緒に煮られた豆腐やネギとも相性がよかった。
お腹いっぱい食べた私に、彼は珈琲とアイスクリームまで注文してくれた。
アイスクリームは口の中を優しい甘さと冷たさで癒す。
同じく初体験の珈琲もとても風味がよくてびっくりした。
「ちょっと苦いけどおいしいです」
洋服店で泥水みたいとか思ってごめんなさい。
馨様はさっき珈琲を飲んだので、ここではお茶を飲んでいる。
「やっと笑ったな。うたは洋服より牛鍋が好きなようだ。覚えておこう」
「えっ。ど、どっちも同じくらい好きですよ」
たしかに洋服を作るときは緊張しっぱなし、恐縮しっぱなしで、顔が強張っていたかもしれない。
けれど、色気より食い気と思われると、非常に心外だ。
お腹が空いていたのと、牛鍋が存外おいしかったので、ちょっとがつがつしすぎたかも。恥ずかしい。
意識して、残りのアイスクリームはゆっくり食べた。
私が食べ終わるまで、馨様は目を細めてこちらを見つめていた。
食事を終えたあと、私たちは芝居小屋で歌舞伎を見た。
演目は『忠臣蔵』。
初めて見る迫力ある役者の演技に圧倒され、最後は感動で胸が熱くなった。
芝居小屋の前で売られていた役者の錦絵を買ってもらい、私はそれを抱きしめて歩く。
「さて、そろそろ日が暮れるな。帰るとするか」
「はい」
こんなに楽しかった一日は、生まれて初めてだった。
豪華な洋服や食事よりなにより、想いを寄せる人と一緒に過ごせたことがうれしい。
馨様も、今日はよく笑ってくれた。
出会った頃は仏頂面ばかりだった彼が笑ってくれると、私まで頰が緩む。
ふと空を見ると、夕陽が白い建物の壁面を赤く照らしていた。
増した寒さに、充実した一日の終わりが近づいていることを実感し、切なくなった。
「また一緒にお出かけできるでしょうか……」
乗合馬車に乗り、桐野邸に一番近い停車場で降りたときには、辺りはだいぶ暗くなっていた。
「ああ。また非番の日は一緒に出かけよう」
停車場から桐野邸までは、少し歩かねばならない。
私たちは残りの時間を惜しむように、ゆっくりと歩を進める。
「夢みたいでした。あなたと一緒に、見たこともないものをたくさん見られて」
あの家から出なければ、一生縁がなかったものもあっただろう。
馨様が私を連れて逃げてくれたおかげで、世界が広がる。
この夢が、いつまでも続けばいいのに。
「楽しかったか」
「はい、とっても」
「俺も。生まれて初めて、楽しいという感覚を味わった気がするよ」
見上げると、馨様は晴れ晴れとした横顔をしていた。

