書籍詳細
エリートパイロットは初心な彼女への滴る最愛欲を隠せない
あらすじ
「君を独占する権利が欲しい」
極上パイロットに溺れるほど甘やかされて♡
恋愛未経験のグランドスタッフ・美羽は、男性に絡まれていたところを憧れのパイロット・晴翔に助けられる。それをきっかけに、彼の甘い溺愛が開始!?「恥ずかしがる姿も可愛い」――優しくもSっ気全開に美羽を翻弄する晴翔。初心な美羽の態度が晴翔の独占欲をますます煽り、普段はクールな彼にとろけるほどの愛情を注がれ、隅々まで溶かされて…。
キャラクター紹介
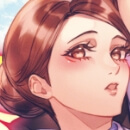
春川美羽(はるかわみう)
国内最大手の航空会社『Japan Wing Airlines』のグランドスタッフ。趣味は航空機の写真を撮ること。

天堂晴翔(てんどうはると)
若き副操縦士。クールだけれど、仕事へのストイックさからスタッフの信頼は厚い。機長昇格は間近と言われている。
試し読み
天堂さんの家に行くことになったのは、それから四日後のことだった。
夜勤明けだった私は、一度帰宅して仮眠を取り、仕事帰りに迎えに来てくれた彼とスーパーに立ち寄った。
まだ時間が早いから、ふたりで夕食を作ろうということになったのだ。
今日は国内線の担当だった天堂さんは、明日は午後からスタンバイらしい。
彼からは『ゆっくり過ごせるよ』と言われている。
「嫌いなものとかありますか?」
「ないよ。だいたいなんでも食べられる」
「じゃあ、和食と洋食ならどっちがいいですか?」
「家で食べるなら和食がいいな。海外にいると洋食続きになるし、日本にいるときはできるだけ和食を摂るようにしてるんだ」
パイロットは、ライセンス取得後も定期的に厳しい検査を受けなくてはいけない。
以前に聞いた通り、健康管理は仕事の一環だと言える。
適度な運動はもちろん、食生活や睡眠は特に重要で、きっと体調管理には気を遣っているに違いない。
色々と相談しながらカゴの中に食材を入れていく。
調味料はある程度は揃っているらしく、買ったのは魚や野菜ばかりだった。
こうしてふたりで買い物をしていると、まるで新婚のような気分になる。
そんな妄想をしてしまう自分自身に呆れつつも、楽しくて仕方がなかった。
天堂さんの家に着くと、仲良くキッチンに並んだ。
自炊をしているだけあって、彼の手際はとてもいい。
緊張のせいか、私の方がもたつきがちだった。
「天堂さんって、なんでもできるんですね」
「そんなことないけど」
「それこそ、そんなことないと思います。天堂さんの方が料理上手な気がしますし」
「俺、いつも味付けは適当だよ。塩分を摂りすぎないように気をつけるくらい」
天堂さんは苦笑しつつも、あっという間に人参の千切りを終え、包丁で蓮根の皮も剥いてしまう。
その手つきを見ていると、器用なのがよくわかった。
「それに、俺は美羽の味が知りたいんだ」
柔らかい笑みを前に、なんだか深読みしてしまう。
私の〝料理の〟味が知りたいと言われているだけ。
それなのに、脳裏に過ったのは今夜のこと。
(……ッ! なに考えてるの……っ!)
意識するな、という方が難しい。
嫌でも、このあとのことばかり想像してしまう。
けれど、今は目の前のことに集中しなければ料理の完成が遠のいていきそうで、なんとか心を落ち着かせた。
旬のスズキの塩焼き、蓮根と人参のきんぴら、ほうれん草の胡麻和え、きゅうりの酢の物、そしてトマトたっぷりのサラダと豆腐のお味噌汁。
ふたりで分担して完成させたメニューは、心配を余所においしくできた。
天堂さんはとても喜んでくれ、「おいしい」と繰り返し口にしていた。
そんな穏やかなひとときのあとには、緊張の時間が待ち受けていたのだけれど。
(どうしよう……。口から心臓が飛び出しそう……)
比喩表現だと思っていたのに、さきほどからずっと緊張しすぎて心臓がうるさい。
本当に飛び出すんじゃないかと勘違いするほど、バクバクと鳴っていた。
先にお風呂を借りた私と交代で、今は彼がバスルームにいる。
どこでどんな風に待てばいいのかわからなくて、リビングをさまよってはソファに戻り、また立ち上がる。
天堂さんとは付き合ってからも何度か会っているけれど、彼の家に来るのはまだ二度目。
初めてのお泊まりというのもあって、平常心でいる方が無理な話だ。
このままでは心も身体も持ちそうになくて、緊張を忘れるためにスマホを取った。
【頑張れ! 緊張しすぎないようにね】
【リラックスですよ! あと、勝負下着をつけ忘れちゃダメですからねー】
ところが、華と愛子ちゃんとのメッセージグループの通知を見た瞬間、緊張がピークに達してしまった。
バルコニーの向こう側に見える空には、蜂蜜色の月が輝いていた。
地上よりも空に近いからか、わずかな星たちが微かに瞬いているのも見える。
「なにか見える?」
不意に飛んできた声に、肩がピクリと跳ねる。
ぼんやりと外を見ていたせいで、天堂さんがバスルームから戻ってきたことに気づいていなかった。
「月と、星が少しだけ……。ここは空に近いので、星が瞬いてるのもわかりますね」
「そう? 家で星なんてあんまりじっくり見ないから気にしてなかったな」
隣に並んだ彼が、全面がガラスになった窓越しに外を覗く。
「ああ、確かに。下にいるときよりはわかるな」
ふと視線を感じて右側を向くと、天堂さんがこちらをじっと見ていた。
「あの……」
「ああ、ごめん。ルームウェア姿が新鮮だなと思って」
微笑まれて、思わず彼から視線を逸らしてしまう。
頬がかあっと熱くなった。
「可愛いよ」
天堂さんの瞳が弧を描く。
柔和な笑みを前に、ドキドキするばかり。
今からこんな状態だと、このあとどうなるのか想像もつかなかった。
「おいで。こっちでゆっくり話そう」
手を引かれてソファに誘われ、彼が先に腰掛ける。
ところが、肘置きを背にして横向きに座ったから、私はたじろいでしまった。
けれど次の瞬間、私の手を掴んだままの天堂さんの方へ体が傾いた。
「えっ……?」
最初はなにがどうなったのかよくわからなかった。
状況が把握できたときには、私の体は彼の胸の中にすっぽりと収まっていた。
「あ、の……ッ」
背中に感じるのは、天堂さんの硬い胸板の感触と体温。
「ん?」
頭頂部にくちづけられ、髪に彼の吐息も触れる。
「えっと、この体勢は……?」
「美羽が緊張してるみたいだから、ちょっとリラックスしてもらおうかと思って」
(余計に緊張します……!)
心の中で叫んでも、当然ながら背後にいる天堂さんは動じる様子はない。
広いソファの上で、ゆったりと伸ばされた長い足。
その間に座らされている私は、リラックスするどころか体が強張ってしまう。
「わ、私……っ、すごく重いので……!」
ようやく逃げようとしたのに、彼の腕が私を捕まえにくる。
「こら、逃げないで」
後ろから抱きすくめるがごとく前に回った手が、私の体を包み込んでしまった。
「で、でも……」
「全然重くないし、むしろ軽いくらいだよ。ちゃんと食べてる?」
「そ、それはもうっ……! 毎日モリモリ食べてます!」
なぜかそんな返答をした私は、自分の答えと今の状況のせいで羞恥が大きくなる。
せめて少しでも体重をかけないようにしようと身じろいでみると、天堂さんの腕にいっそう力がこもった。
「逃がさないって。力で敵うわけがないんだから、大人しく抱きしめられなさい」
不服そうでいて楽しげな声音が、私の鼓膜をくすぐる。
逃げられないことを悟って諦めると、彼はクスッと笑った。
「今はまだなにもしないから、安心していいよ」
言葉に反して、天堂さんの唇は私の頭に触れている。
頭頂部、こめかみ、後頭部。
ひとつひとつを愛でるように、キスが落とされていく。
「なにもしないんじゃ……」
「ちょっと唇で触れてるだけだよ」
ごく普通に返されてしまったものだから、納得しそうになる。
それがおかしいと気づけないほど、私は緊張でいっぱいだったのだ。
「シャンプーの匂いがする。こういうの、いいな」
嬉しそうな彼からも、爽やかな香りが漂ってくる。
シャンプーとボディーソープが混ざった匂いに包まれて、脳がクラクラと揺れるようだった。
「……天堂さんって、こういうことする人だと思ってませんでした」
「俺も」
「え?」
「美羽と付き合うまで、自分が恋人に対してこんなに甘い雰囲気を出すとは思ってなかったよ」
それは、ただのリップサービスだったのかもしれない。
天堂さんがそう言っているだけで、本当は恋人には甘い態度を取る人なのかもしれない。
そんな思考とは裏腹に、心には喜びが突き上げてくる。
ただ、恥ずかしさをごまかしたかったのに、余計に羞恥が大きくなった。
「自分からくっつきたいなんて思うこともなかったんだけどな」
こんな風に、と囁いた彼の腕がギュッと私を抱きしめ、耳朶に唇が落とされる。
「美羽といるとずっとくっついていたくなるんだけど、どうしてくれるんだ」
そんなことを私に言われても困る。
どうしてくれるんだ、と問いたいのは、むしろ私の方だった。
恋愛に初心者マークがあるなら十枚は貼りつけているだろう私には、この状況への対応力なんてあるはずがない。
「今でも離れたくないのに、明日出勤するのが嫌になりそうで困るよ」
私の髪を耳にかけ、無防備になった耳殻に唇を寄せながら囁いてくる。
恋愛上級者の雰囲気を醸し出す天堂さんの低い声音に、胸がきゅうっと震える。
私の思考を溶かすには充分すぎる彼の態度に、鼓動は大きく速くなっていく。
(こういうときって、どうするのが正解なの……)
恥ずかしさといたたまれなさで、体が微かに震えている。
きっと、緊張したり動揺したりしているのは私だけで、天堂さんは顔色ひとつ変えていないに違いない。
振り向く勇気はなかったけれど、そうだとしか思えなかった。
「美羽?」
「……ッ、はい……」
顔が沸騰しそうなほどに熱くて、彼に名前を呼ばれただけで眩暈がする。
「顔、見せて?」
「今はちょっと……」
「大丈夫。俺しか見てないから」
たじろぐ私を、天堂さんが優しく誘おうとする。
あなたに見られるのが一番恥ずかしいんです……とは言えなくて、少しだけ悩んだ末にゆっくりと振り返った。
刹那、彼の真っ直ぐな瞳と目が合った。
頬に添えられた手が、私の顔を上に向かせる。
吐息が触れそうな距離にいる天堂さんの眼差しは、わずかな優しさを覗かせながらも真剣だった。
戸惑いを隠せずにいると、そっと唇を塞がれてしまった。
労わるような優しいくちづけに、胸の奥が甘やかな音を立てる。
再び唇が触れ合うと、もう逃げる術はないのだと悟らされた。
重なるだけだった唇が啄まれる。
悪戯に、それでいて優しく。けれど、ふとした瞬間にわずかに強く。
私の唇を弄ぶような仕草なのに、やわやわと食まれると心地好くなっていく。
触れるだけのキスよりも先に進んだのは初めてだった。
前に一度、天堂さんの家に来てからは、彼とのデートは仕事の合間を縫って食事に行くくらいの時間しかなくて、ゆっくり会えたのはあの日以来だったから。
デートの別れ際に与えられるキスはいつも優しく触れるだけで、それよりも深くなることはなかった。
だから、なにをどうすればいいのかなんてわからない。
戯れのようなキスに思考が鈍り、今でもいっぱいいっぱいだったのに……。
「……ッ、ん……」
酸素を求めて開いた唇の隙間から舌が入ってくると、甘えたような声が漏れた。
自分のものではない熱が、私を暴こうとする。
わずかな強引さで口内をゆっくりと探られ始め、くすぐったさと知らない感覚に襲われる。
背筋がゾクッと震えて、息が苦しくなっていった。
舌先が口腔を撫で、歯列をたどり、顎の裏を舐められる。
頭がおかしくなりそうなほどの熱が押し寄せて、上昇する体温と乱れる息のせいで酸素が足りない。
苦しくてたまらないのに、不思議と天堂さんを止めようとは思わなくて。
「ふ、っ……」
鼻から抜けるような吐息を幾度となく漏らし、気がつけば彼を受け入れることに必死になっていた。
キスはどんどん深くなり、とうとう舌を捕らえられてしまう。
くちづけはさらに甘く深く、天堂さんが私を堪能している。
さきほどよりも強引に、吐息すらも奪うように。
絡み合った舌の感触を楽しむような行為の中に、ほんの少しだけ優しさを残して。
そのまま極めつけに舌を吸い上げられると、体の芯からじんじんと痺れた。
ようやくして唇が解放され、私は新鮮な空気を欲して肩で息をする。
すると、彼の骨ばった手が、熱を帯びた私の頬をふわりと撫でた。
「……美羽の顔、真っ赤」
ふっと微笑む様が艶麗で、その色香にドキリとさせられる。
私を見つめる天堂さんの双眸は、どんな言葉よりも雄弁な熱を孕んでいた。
「もっと見せて。美羽の全部が見たい」
その蠱惑的な懇願を、どうすれば拒否できたのだろう。
好きな人の声で甘ったるく紡がれた誘惑は、私の心を簡単に懐柔してしまう。
小さく頷けば、天堂さんが背後から抜け出して立ち上がり、私を抱き上げた。
「やだっ……! 私、自分で歩けます……!」
お姫様抱っこをする彼に反射的にしがみつきながらも、「下ろして……」と請う。
「ダメ。今日は美羽を甘やかすって決めてるんだ」
勝手に天堂さんの中で出来上がっていたルールに、私はただ大人しくすることしかできなくて。せめてもの抵抗で、咄嗟に彼の首に回した手を解く。
「そのまましがみついててよかったのに」
残念そうな声が降ってきたとき、開いたままだった寝室のドアを抜け、クイーンサイズのベッドに下ろされた。
覆い被さってきた天堂さんが、私の額にくちづける。
労わるように、慈しむように。
大切にされていることが伝わってくる、優しいキスだった。
「美羽、好きだよ」
「私も……すき、です……」
「うん。でも、もっと好きになって」
たわんだ瞳が、私を愛おしそうに見つめている。
嬉しそうな彼の表情が、私の心を捕らえて離さない。
胸の奥が苦しいくらいに締めつけられて、恋情がいっそう膨らんだ。
程なくして再び唇が重なり、そっと頭を撫でられて。その手はいつしか首筋に下がり、私の体をゆっくりとたどっていく。
それを追うように、唇が首筋に触れた。
壊れ物を扱うように肌を撫でる唇も、体を愛でる手も、布越しでも熱かった。
けれど、不思議と不安や恐怖心はない。
そのせいか、パステルイエローのパイル地のルームウェアの中に骨ばった手が入ってきても、思っていたほど動じることはなかった。
鍛えられた男性らしい体躯にも、汗で湿った肌にも、脳がクラクラと揺れる。
心も視線も捕らわれて、想いが溢れて仕方がなかった。
誰にも触れられたことがない体を許すのも、すべてをさらけ出すのもドキドキするけれど、触れ合う素肌が心地好くて幸せに包まれる。
抱きしめてくれる腕の力強さに、天堂さんがくれる甘い感覚。
「美羽、好きだ……」
唇と指先が私の全身を何度も愛おしみ、絶え間なく愛を唱えてくれる。
彼から愛されているという実感が湧き上がり、言いようのない喜びと幸福感の中で心が揺蕩っていた――。
翌朝、目を覚ますと、天堂さんは私の額にくちづけた。
「おはよう」
「ッ……おはよう、ございます……」
くすぐったくて穏やかな朝に、羞恥と幸せに包まれた胸がドキドキする。
「美羽。そろそろ敬語はやめて、名前で呼んでよ」
「えっと……」
「ほら、呼んでみて」
甘い笑顔が、戸惑う私を誘惑する。
「はると、さん……?」
恥ずかしさを抱えながらも呼んでみると、彼が幸せそうに破顔した。
眩しいくらいの笑顔に、胸の奥がキュンキュンと戦慄く。
ほんの三か月ほど前までは、恋人どころか恋愛にも無縁だった。
それなのに、今は素敵な恋人にとても大切にしてもらっている。
嬉しいのに、本当にこんなにも幸せでいいのか……なんて考えてしまった。
「美羽。朝食はフレンチトーストとかどう?」
「あ、いいですね。フレンチトースト、大好きです」
「じゃあ、俺が作るよ」
「天堂さんが?」
「言っただろ。美羽を甘やかすって決めてるって」
砕けた笑みを浮かべた天堂さんは、私の額と鼻先に唇を落としたあと、唇にも触れるだけのキスをくれた。
「でも、あともう少しだけ抱きしめさせて」
ぎゅうっと抱きしめられて、彼の匂いと体温に包まれる。
「それと、名前で呼ぶのと敬語をやめるのは、美羽への課題にするから」
「え?」
「期限は次に会うまで。もしできなかったら……そうだな、空港でキスしようか」
「ダッ……! ダメですよ、そんなの!」
天堂さんは悪戯な笑顔で「楽しみだな」と零すと、再び私の唇を奪った。
甘くて優しいキスに、少し前に感じた不安は溶けて消えてしまう。
「……本当に離れがたくなってきたな」
ひとりごちるように言った彼は、ますます私を力強く抱きすくめた。
「私も……離れるのが寂しいです……」
「じゃあ、一緒にいる間にたくさんくっついていようか」
「はい」
優しい手が私の髪を梳き、柔和な眼差しを向けられる。
午前八時の寝室は、甘ったるい雰囲気に包まれていた。

